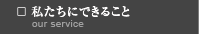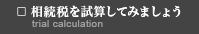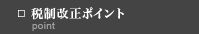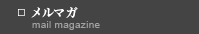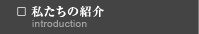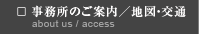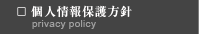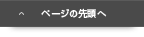〔平成26年1月1日施行〕延滞税の割合が軽減
改正の概要
期限後申告や修正申告により未納税額の納税を行う場合には、法定納期限の翌日からその未納税額を完納する日までの期間に応じて延滞税が課されます。
この延滞税の割合が改正され、軽減される事となりました。
延滞税の計算
原則として延滞税は、法定納期限の翌日から未納税額を完納する日までの期間に応じて日割りで課税されます。
延滞税と税務調査
期限後申告による未納税額の納付は別として、修正申告の場合は、一般的に税務調査を受けた事により未納税額が発生するケースが多いと思います。
税務調査
税務署が、納税者の申告内容が正しいかどうかをチェックするために行う調査の事です。
通常の税務調査は、任意調査と呼ばれるものであり、納税者の同意の下で実施されます。
一方、強制調査と呼ばれるのは、国税局の査察部が、国税犯則取締法により裁判所の令状を得
て実施する査察調査(いわゆる“マルサ”)のことです。
しかし、税務調査は、法定申告期限を過ぎてから実施され、場合によっては法定申告期限から2~3年後に実施されるケースも珍しくありません。
このような場合、原則どおりに法定納期限まで遡って延滞税を起算し、未納税額を完納した日までの期間に応じた延滞税を課されてしまうと、ケースによっては非常に高額の延滞税を課されてしまいます。
延滞税の控除期間の特例
そこで、延滞税の計算を行う際には、上記のような過剰な税負担の発生を考慮し、延滞税を計算する際の期間に特例が設けられています。
特例の内容
この特例には、いくつがパターンがあるのですが、例えば、期限内申告書を提出し、その法定申告期限から1年を経過する日後に修正申告書を提出した場合についてみてみましょう。
控除される期間
この場合、延滞税を計算する上で控除される期間は、次のとおりです。
■その法定申告期限から1年を経過する日の翌日からその修正申告書が提出された日までの期間
例えば、法定申告期限が、平成26年3月31日、修正申告書の提出日を平成27年6月30日と仮定すると、
■法定申告期限から1年を経過する日⇒平成27年3月31日
■ (同上) の翌日⇒平成27年4月1日
となります。
よって、延滞税の計算上控除される期間は、『平成27年4月1日~平成27年6月30日』までの期間となります。
つまり、延滞税が課されるのは、『法定申告期限から当初1年間のみ』という事になります。
注意点
但し、注意点があります。
控除される期間は、『修正申告書が提出された日』までの期間です。
よって、修正申告書の提出日の翌日以降に未納税額を納付した場合には、修正申告書の提出日の翌日から未納税額を納付した日までの期間は、延滞税が課される事となります。
修正申告による納税は、修正申告書の提出と同時に済ませるようにしましょう。
また、税務調査の結果、重加算税の対象となる仮装隠ぺい行為が発見された場合は、この控除期間の特例は適用されませんので、注意が必要です。
延滞税の割合
延滞税の割合は、下記のとおりです。
改正前
■原則
年14.6%
■特例(納期限までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間)
年7.3%
改正後
上記の割合が、下記のとおり改正されました。
■原則
年9.3%
■特例(納期限までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間)
年3%
適用開始時期
この改正は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税から適用されます。